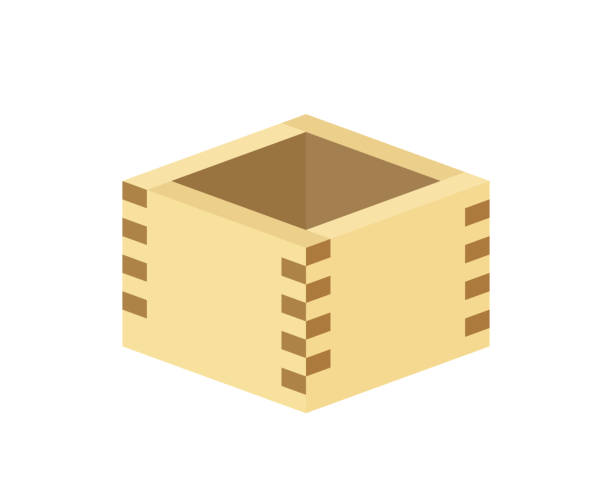
【龍空】量る器から、願う器へ――枡に込められた日本の心
【枡(ます)の歴史】
日本の伝統文化の中で、「枡(ます)」ほど身近で奥深い道具はありません。もともとは「量(かぞ)える」ための器として誕生しましたが、今では祝い事や神事、そして酒席などでも欠かせない存在です。その小さな木箱には、日本人の暮らしと美意識がぎゅっと詰まっています。
枡の起源は古く、奈良時代にまでさかのぼります。当時、中国から律令制度とともに「度量衡(どりょうこう)」の概念が伝わり、日本でも米や穀物を量るための基準が整えられました。その中心となったのが「升(しょう)」という単位で、これが後に「枡」という形の器に姿を変えていきます。平安時代にはすでに木製の枡が使われており、庶民の生活の中で欠かせない日用品となっていきました。
江戸時代になると、枡は商売や経済の基盤としてさらに重要な役割を果たします。米は「経済の中心」であり、税も年貢も米で納める時代。正確な計量が国の信頼を左右しました。そのため、「大坂枡」「江戸枡」など地域ごとに統一規格が定められ、枡づくりの職人たちが高い技術を競い合いました。また、商人が誠実さを示す象徴として、「一合枡」を贈る習慣もあったといわれています。
やがて明治以降、メートル法が導入され、枡は実用品から徐々に姿を消していきます。しかしその美しい形と香り高い檜の風合いは、日本文化の象徴として今も愛され続けています。酒を注げば「ますます繁盛」、祝いの席では「福をます」という縁起の良い言葉にもつながり、枡は「量る器」から「願いを込める器」へと変化しました。
現代では、枡は観光地の記念品や、カフェのデザート容器としても人気です。古くから受け継がれた木の温もりと、どこか懐かしい香り。千年以上の時を超え、枡は今も日本人の心に「豊かさ」を伝え続けています。

